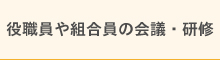2025年新年講演会を開催しました
1月16日(木)、都シティ大阪天王寺「吉野の間」にて、2025年新年講演会を開催しました。当日は73名の参加がありました。5年ぶりの開催となる今年の新年講演会は、日本協同組合連携機構(JCA)の比嘉政浩様(代表理事専務)を講師にお招きし、「協同組合のアイデンティティと持続可能な社会の実現に向けて~IYC2025をうけて~」をテーマにご講演いただきました。大阪ご出身ということで、聞きなじみのある大阪弁でわかりやすくお話いただきました。
まず、2025年を二度目の国際協同組合年(IYC2025)とした背景や、協同組合に対する国連の評価や期待についてご紹介いただきました。
次に、IYC2025全国実行委員会から各協同組合への3つの行動提起について報告されました。IYCをチャンスと捉え、1人でも多くの人に「協同組合を知ってもらう(発信する)」こと、生協役職員が「自分の言葉で」協同組合の魅力を発信できるように「学ぶ」こと、が提起されました。また、協同組合の「目的(使命)」と「収支確保」が両立する事業方式の事例も紹介され、両立には「志」「効率的・効果的なビジネスモデルの構築」「組合員の参加(役割発揮)」が必要とのお話をいただきました。
最後に、協同組合間連携の経過や事例が紹介され、地域社会の課題解決に向けた連携・協力の広がりについてお話いただきました。
その後、4~5人のグループに分かれてグループ交流を行いました。講演の感想や「協同組合の魅力や好きなところ」「2025年に協同組合としてチャレンジしてみたいこと」についての意見を交流しました。交流後、6つのグループより交流された内容について発表され、比嘉様から講評をいただき講演会を終えました。
〈参加者アンケートより抜粋〉
【比嘉専務の講演を聞いての感想】
・どおりでお話が聞きやすいと思えば大阪弁!わかりやすく頭に入ってきました。せっかくの国連が推してくれている「協同組合年」。時間がなくならないうちに早く取り組みを進め、多くの人にアピール、浸透できるようにしたいです。具体的な取り組み方もご教示いただけたことですし。
・国連がなぜ協同組合を評価しているのか、協同組合の価値を理解しそれを自分の言葉で、説明することが大切であること。IYCは多くの方に協同組合を知って頂ける、また、各協同組合が積極的な取り組みを進めていき、連携を進めていけるチャンスであること。比嘉様のお話を聞き、何ができるのかしっかり考えていきたいと思いました。
・とても親しみやすい口調での講演はあっという間でした。国際協同組合年は協同組合の輪を広げるチャンスであること。そして、自分でできることは、学び、自分の言葉で良さを伝えていくこと。協同組合の理解者を増やすことが大事だという事を今回の講演で学びました。
・協同組合でも助けあいの精神のもと、社会の課題に早くから取り組んでいると思っていますが、認知度がまだまだ低く、評価されていないのだなと改めて感じました。"国際協同組合年"ということを知らせる、いいきっかけの年になるので、動画やバッジを活用して、コトバにしていくことも大切だと思いました。
【グループ交流を通じて考える「協同組合の魅力」】
・グループ交流では、大学生協から「大学生は生協を知らないひとが多く、日本固有のものでダサイと考えている」と発言され、改めて若い世代に協同組合を知ってもらう活動が緊急課題だと感じた。歯車の1つでなく、みんなで出資・運営・利用を基本に意見を出し合い、責任をもって行動し、楽しいことも・しんどいことも分け合うことができる所が魅力だと思います。
・今回の会議もそうですが、地域生協、医療生協、大学生協、共済生協と展開している事業は全く異なっているのに「協同組合」という枠組みでつながりを持てていることが魅力だと感じています。
・助け合いの組織というのが、どの協同組合にも共通していて、ノウハウを教えあったり災害時に駆け付けたり、みんなの力でなんとか良い方向にできるというのが魅力だと感じた。
・①つながりがあること。平和や災害時にそれが発揮できるところ。②いろんな形で社会活動に参加できる機会を作ってくれていること。③学び、学びあえる機会を作っていること。そこから行動に移せる人を増やしていること。
1月16日(木)、都シティ大阪天王寺「吉野の間」にて、2025年新年講演会を開催しました。当日は73名の参加がありました。5年ぶりの開催となる今年の新年講演会は、日本協同組合連携機構(JCA)の比嘉政浩様(代表理事専務)を講師にお招きし、「協同組合のアイデンティティと持続可能な社会の実現に向けて~IYC2025をうけて~」をテーマにご講演いただきました。大阪ご出身ということで、聞きなじみのある大阪弁でわかりやすくお話いただきました。
まず、2025年を二度目の国際協同組合年(IYC2025)とした背景や、協同組合に対する国連の評価や期待についてご紹介いただきました。
次に、IYC2025全国実行委員会から各協同組合への3つの行動提起について報告されました。IYCをチャンスと捉え、1人でも多くの人に「協同組合を知ってもらう(発信する)」こと、生協役職員が「自分の言葉で」協同組合の魅力を発信できるように「学ぶ」こと、が提起されました。また、協同組合の「目的(使命)」と「収支確保」が両立する事業方式の事例も紹介され、両立には「志」「効率的・効果的なビジネスモデルの構築」「組合員の参加(役割発揮)」が必要とのお話をいただきました。
最後に、協同組合間連携の経過や事例が紹介され、地域社会の課題解決に向けた連携・協力の広がりについてお話いただきました。
その後、4~5人のグループに分かれてグループ交流を行いました。講演の感想や「協同組合の魅力や好きなところ」「2025年に協同組合としてチャレンジしてみたいこと」についての意見を交流しました。交流後、6つのグループより交流された内容について発表され、比嘉様から講評をいただき講演会を終えました。
〈参加者アンケートより抜粋〉
【比嘉専務の講演を聞いての感想】
・どおりでお話が聞きやすいと思えば大阪弁!わかりやすく頭に入ってきました。せっかくの国連が推してくれている「協同組合年」。時間がなくならないうちに早く取り組みを進め、多くの人にアピール、浸透できるようにしたいです。具体的な取り組み方もご教示いただけたことですし。
・国連がなぜ協同組合を評価しているのか、協同組合の価値を理解しそれを自分の言葉で、説明することが大切であること。IYCは多くの方に協同組合を知って頂ける、また、各協同組合が積極的な取り組みを進めていき、連携を進めていけるチャンスであること。比嘉様のお話を聞き、何ができるのかしっかり考えていきたいと思いました。
・とても親しみやすい口調での講演はあっという間でした。国際協同組合年は協同組合の輪を広げるチャンスであること。そして、自分でできることは、学び、自分の言葉で良さを伝えていくこと。協同組合の理解者を増やすことが大事だという事を今回の講演で学びました。
・協同組合でも助けあいの精神のもと、社会の課題に早くから取り組んでいると思っていますが、認知度がまだまだ低く、評価されていないのだなと改めて感じました。"国際協同組合年"ということを知らせる、いいきっかけの年になるので、動画やバッジを活用して、コトバにしていくことも大切だと思いました。
【グループ交流を通じて考える「協同組合の魅力」】
・グループ交流では、大学生協から「大学生は生協を知らないひとが多く、日本固有のものでダサイと考えている」と発言され、改めて若い世代に協同組合を知ってもらう活動が緊急課題だと感じた。歯車の1つでなく、みんなで出資・運営・利用を基本に意見を出し合い、責任をもって行動し、楽しいことも・しんどいことも分け合うことができる所が魅力だと思います。
・今回の会議もそうですが、地域生協、医療生協、大学生協、共済生協と展開している事業は全く異なっているのに「協同組合」という枠組みでつながりを持てていることが魅力だと感じています。
・助け合いの組織というのが、どの協同組合にも共通していて、ノウハウを教えあったり災害時に駆け付けたり、みんなの力でなんとか良い方向にできるというのが魅力だと感じた。
・①つながりがあること。平和や災害時にそれが発揮できるところ。②いろんな形で社会活動に参加できる機会を作ってくれていること。③学び、学びあえる機会を作っていること。そこから行動に移せる人を増やしていること。
 日本協同組合連携機構(JCA)
日本協同組合連携機構(JCA)比嘉 代表理事専務
 12グループに分かれて
12グループに分かれて交流しました
 「協同組合の価値・魅力」に
「協同組合の価値・魅力」について話が盛り上がりました
 各グループで交流した内容を
各グループで交流した内容を全体で発表しました
 グループ交流で見つけた
グループ交流で見つけた「協同組合の魅力」を発表